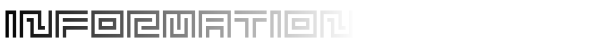12.12.22:20
[PR]
06.26.08:12
Delightful
なんか、昨日は基本的人権における
外国人の人権享有主体の
公務員就任権の判例理論を
詳しく調べたら、また引き込まれた。
いわゆる、
管理職選考受験資格確認請求事件である。
公権力の行使または、
国家意思の形成への参画への排除を
しめした内容だった。
学説の中では人権制約基準としては
広汎かつ抽象的で違憲の疑いが強い
という見方もある。
いわゆる、定型的で技術的な職務なら
外国人も就任可能となる。
参政権の性質と扱われるからこそ
「・・・国民主権の原理に基づき国及び
普通地方公共団体による統治の在り方に
ついては日本国の統治者としての国民が
最終的に責任を
負うべきであること(憲1条、15条一項)・・・・」
という一文に心に響いた。
地方公共団体の首長への被選挙権では、
法定受託事務を担任する以上は国民主権の
原理からして担当者は日本国民に限られる
という指摘も納得できた。
22条一項の公務員就任権への判断を
回避した最高裁判例であり、
公務員選定権を公務員就任権に
置き換えて判断したことへの論理の飛躍
という批判もされていた。
私見としては、
日本国以外の国家に属している以上は
国民主権の原理からして、
合理的な基準による
制限は認められて当然のように
思われる。
日本国の形成主体は、国民である以上は
外国人の権利と国民の権利の
権利の性質の違いは
考慮すべきだと考える。
しかし、14条の法の下の平等の違反と
なるためにより合理的な理由が更に検証されるべき
だと考える。
憲法における当然の法理と想定の法理の
関係性も注意深く考えなくてはいけない。
PR
- トラックバックURLはこちら