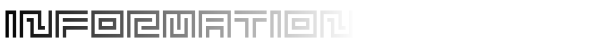06.20.18:32
[PR]
01.06.23:40
火曜日
今日は授業にでて行政法の出題範囲を知った。
憲法に出て、向井先生が執筆なされた本が
3月出版されることになり、購入して早くよんで
みたいなぁと思った。
裁判員制度について力説なされていて、
とても感銘を受けた。
この大学に入って向井先生の講義に出席し
ご教授して頂けることを喜びに思う。
やはり、憲法14条の規定にも関わることも指摘しつつ
80条で明快に説明する先生の説得力がすごかった。
裁判員制度が肯定れると旧司法試験で扱われていた問題の
司法と裁判所の関係性を説明できなくなることを危惧なされていた。
行政と立法は自ずとやるが、司法に関しては自らが動かなくて
はいけない。
裁判所で扱われる法的事実に対して法令を適用することによって
解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争を職業裁判官が
行うことだろう。
下級審の裁判官は内閣が任命するが、
裁判員は所管である地方裁判所が任命するわけで
内閣ではない。
すなわち、裁判官と裁判員をイコールと捕らえてはいけないし
裁判員が地裁から任命を受けるのあれば、裁判書記官などが
判示を書いてもおかしくはないだろうとユーモラスに解説なされていた。
法務省は、裁判を受ける場合に職業裁判官に裁かれなくてはいけない
ということを憲法には規定していないとしているそうだが
司法と裁判所の関係性への回答をしていないことも指摘されていた。
結論、裁判員制度は日本には馴染まないし、失敗すると断言していた。
なぜななら、日本人はディベートする技術もないし
自己主張する文化でもない事をあげていたし、
制度そのものの矛盾も指摘していた。
そして、日本人は特に裁判所から封筒が来ただけで
震え上がる民族だからと冗談を言っていた。
来週は憲法の試験で憂鬱だが、
向井先生の講義を受講したことによって
より一層、憲法が好きになれた自分がいた。
法律学の勉強は自分で条文に意味を与えることが面白さだと
おっしゃっていたが、そのレベルに達したいなと思った。
判例六法と肢を買う検討。
百選の改訂を調べることを視野に入れる。
体系書の補充も検討すること。
会社法の神田
刑総 前田か山口
刑各 西田
憲 芦辺 と高橋
民訴 伊藤?
刑訴 田口か前田
行政 宇賀を検討
ってか、うーん。
むずいな。
勉強に王道なし。
- トラックバックURLはこちら